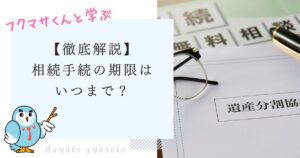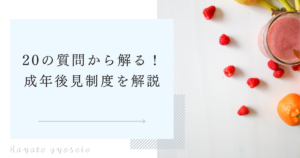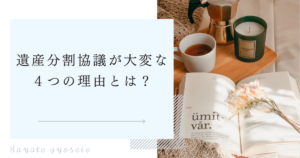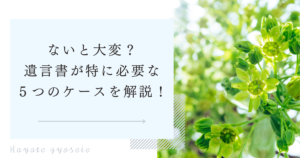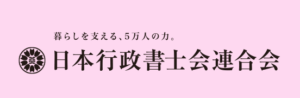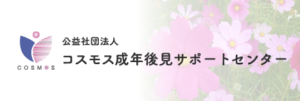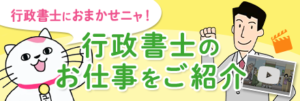【成年後見制度には種類がある?】法定後見と任意後見の違いをわかりやすく解説します!
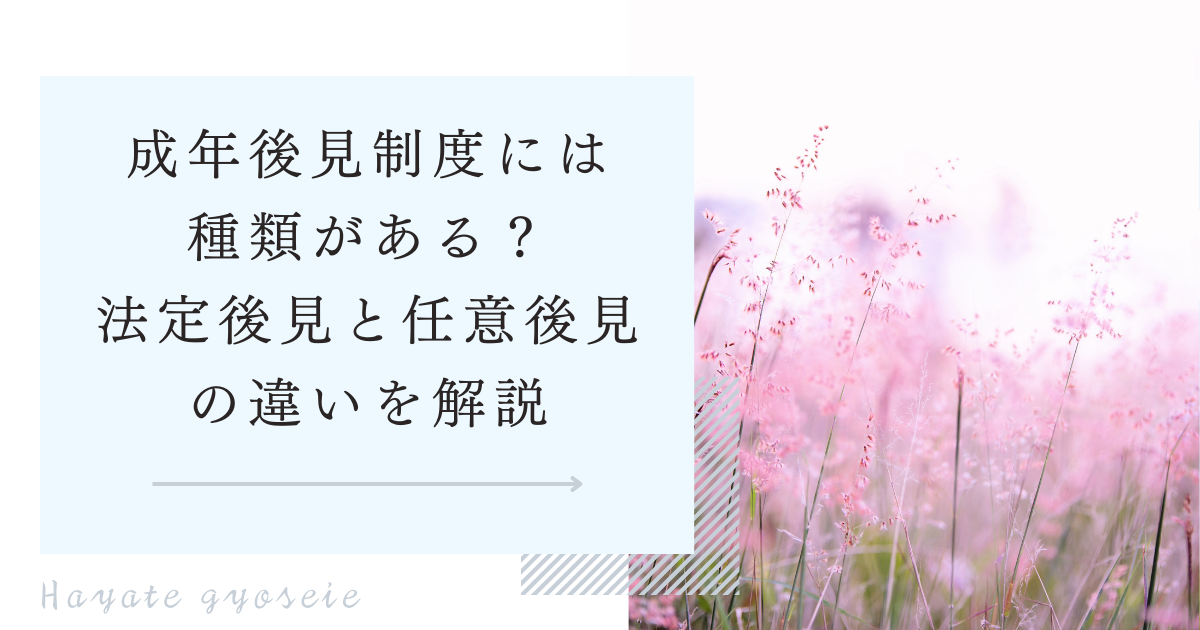
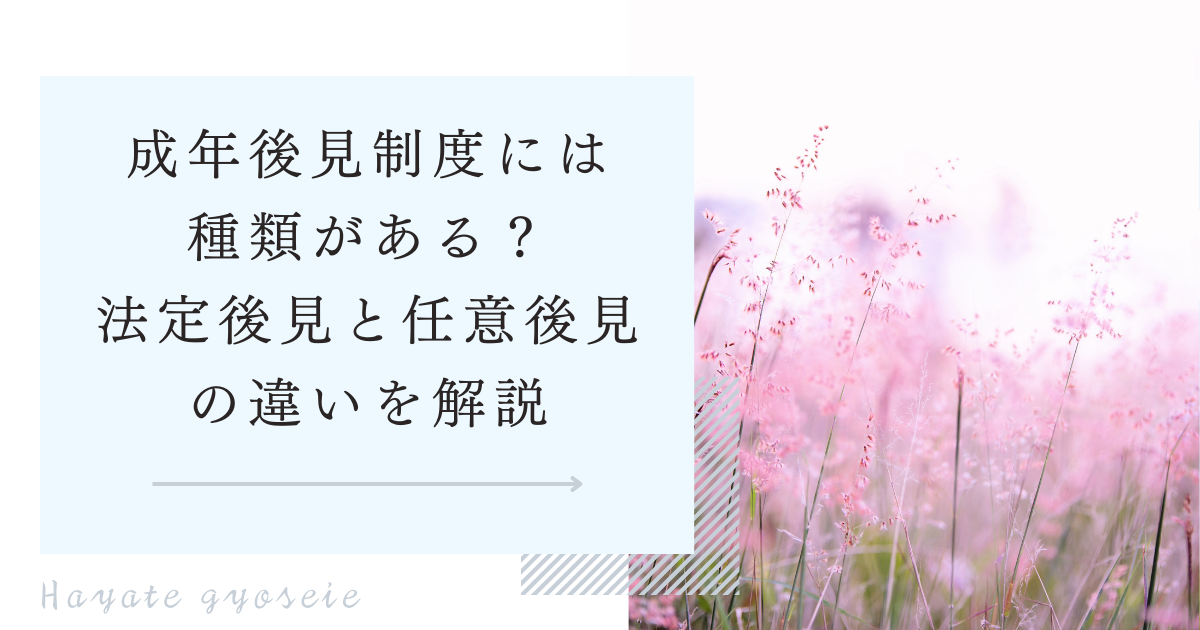
親の認知症が進んできたけど…成年後見制度ってなに?成年後見制度の種類がよく分からない。施設に入居している身寄りがない方、この先後見人が必要?
認知症や知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が低下し、ひとりで法律行為を行うのが難しい場合があります。
自分に不利益な契約であることが分からないまま契約を結んでしまったり、悪徳商法の被害者になってしまうこともあります。
そのような方々を法的に保護し支援するのが成年後見制度です。
この記事では、成年後見制度の種類「法定後見」と「任意後見」について、パラリーガル兼行政書士として100件以上の成年後見案件に携わってきた私が解説します。
今必要な方にもこれからの方にも、それぞれにあった制度を知っておくことが大切です。この記事を読むことで、法定後見と任意後見の違いや権限の違い等を知ることができます。
それでは、解説していきましょう。
法定後見と任意後見の違いとは
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」2種類の制度があります。
法定後見制度
障害や加齢により、ひとりで決めることが心配な人の、その人らしい生き方と安心法的に保護して支援する制度です。
本人の判断能力が低下してから本人、親族等が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力などに応じて3つの類型(後見、保佐、補助)が用意されています。
任意後見制度
この先あれこれ決められなくなる前に自分らしい生き方を自ら決める制度です。
あらかじめご本人が自ら選んだ後見人「受任者」(任意後見人)に、ひとりで決めることが心配になったときに、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
成年後見制度の種類
ここでは成年後見制度について、「法定後見」「任意後見」それぞれを詳しく解説していきます。
法定後見とは 判断力が低下した人の法的権利を守る制度
例えば認知症が進行して判断能力が衰えた人は、悪徳商法などの詐欺の被害を受けやすくなったり、預貯金の引き出しや契約ができなくなったりするなど、不利益を被る可能性が高まります。そのような状況の人を、法的に保護して支援する制度が「法定後見」です。
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをします。
その申立てにより家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始します。特別の事情がない限り、本人が死亡するまで続きます。
法定後見は、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。
どの類型に当てはまるか、また判断や後見人等(後見人、保佐人又は補助人)を誰にするかは、申立ての理由、医師の診断書、本人との面談などを総合的に検討して家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所から選任された後見人等には、類型によって「代理権」「同意権」「取消権」が与えられ、本人の利益のために、与えられた範囲内で権限を使います。
任意後見とは 判断力が十分あるうちに後見契約を結ぶ制度
任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来的に任意後見人になる人との間で、公正証書で任意後見契約を締結するところから始まります。
文字通り「意」思をもって「任」せる制度ですね。ご自身の信頼できる家族や専門職と契約を結ぶことができます。つまり任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときの備えとして結ぶ契約です。
やがて本人の判断能力が低下したら、任意後見がスタートします。任意後見をスタートさせるためには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをします。任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を監督します。任意後見監督人は弁護士等の専門職が選任されることが多く、報酬が発生することも理解しておかなければなりません。
任意後見には法的な分類はありませんが、利用形態として「将来型」「移行型」「即効型」に分かれています。
(1)将来型
将来、判断能力が低下したら任意後見を開始する。
(2)移行型
本人の判断能力が十分なときは、第三者が委任契約によって本人の財産を管理する任意財産管理を行い、判断能力が低下すれば任意後見に移行する。
(3)即効型
任意後見契約を締結し、すぐに任意後見をスタートする
法定後見人と任意後見人の権限の違いに注意
後見人等は、本人の利益になることに、その権限を使います。ですので、相続税対策を目的とした生前贈与や、遺産の放棄、株などの積極的な資産運用はできません。
一方で任意後見の場合は、あらかじめ任意後見契約書に運用について契約を結んでおけば、積極的な資産運用が可能です。
この違いは、法定後見と任意後見の始まりにあります。
法定後見は、判断能力が低下した状態から始まるため本人の明確な意思を確認できないため、任意後見と比較すると本人の意向を反映することが難しいのです。
任意後見は本人の判断能力が十分なうちに、自らの意思によって任意後見契約を結びます。したがって受任者の同意は必須であるものの、違法の場合を除き、自由に契約内容を決めることができます。
任意後見には取消権がない
任意後見は、財産管理の方法を自由に選択できる反面、デメリットもあります。
「悪徳業者と高額なリフォーム工事の契約をしてしまった。」
「知り合いの保証人になってしまった。」
などのトラブルがあった際、法定後見制度の成年後見人は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」に当てはまらなければ、成年後見人が本人の法律行為を取り消すことができます。
※類型が保佐・補助であれば、同意権の範囲内で本人の法律行為を取り消すことができます
しかし任意後見人にはこの取消権がありません。
任意後見人の権限が任意後見契約書で定めた代理権の範囲に限定されるため、任意後見人には、本人の行為を取り消せないのです。
本人がした行為を取り消す場合や、任意後見契約書で定めた代理権の範囲を拡張する必要がある場合には、任意後見契約を終了し、法定後見に移行します。
ただし、任意後見制度は本人が自らの意思で選択した制度です。本人意思の尊重の為にも、法定後見への移行は慎重にしなければなりません。
まとめ
「人生100年時代」という言葉が生まれ、日本の高齢化は益々進んでいます。高齢化にともなって、認知症が大幅に増加し、認知症高齢者の推計人数は、現在600万人に達しているとみられています。核家族化も進み、家族の支援を得られる方も減ってきています。高齢者の中には判断能力が低下していることで、財産管理が困難で、日常の生活を維持することが難しく、悪徳商法の被害も増えています。判断能力が十分でないゆえに、行政等に助けを求めることができず、放置されている例も多くあります。
成年後見制度は、誰にとっても他人事ではありません。特に任意契約は、将来、判断能力が低下したときの備えとして結ぶ契約で、本人の意思を強く反映させることも可能です。
成年後見制度を理解することで、自分自身の大切な権利や財産をどのように守っていくかを考えてみましょう。
こんなお悩みありませんか?






なにからはじめたらいいの?
誰に相談したらいいの?
そんなとき、頼れる存在でありたい。
遺言・相続のどうしように寄り添います。
ささいなお悩みもお気軽にご相談ください。
遺言・相続の無料相談は
「にしのみや福祉はやて行政書士事務所」まで
初回60分は無料となります。
出張相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
9:00~18:00(平日)
24時間受付、簡単入力
お問い合わせ・初回無料相談の流れ
以下のお問い合わせフォームに正確にご入力いただき、送信してください。
入力が難しい場合は事務局(はやて行政書士事務所)までお電話でご連絡ください。
TEL:0798-61-8883(平日:午前9時~午後6時)
※面談、外出等で電話が繋がらない場合がございます。
繋がらない場合は留守番電話にメッセージをお願いいたします。後ほど担当者より連絡をいたします。
改めて具体的なご相談内容をお伺いしたうえで、面談日時や場所、面談方法などを調整いたします。
相行政書士が、ご自宅や入所先の施設・入院先の病院を訪問し、ご本人様またはご家族の方などからの相談をお聞きいたします。事務所(西宮市寿町)での面談も可能です。
お問い合わせフォーム
以下のお問い合わせフォームに正確にご入力いただき、送信してください。
入力が難しい場合は事務局(はやて行政書士事務所)までお電話でご連絡ください。
TEL:0798-61-8883(平日:午前9時~午後6時)
※面談、外出等で電話が繋がらない場合がございます。
繋がらない場合は留守番電話にメッセージをお願いいたします。後ほど担当者より連絡をいたします。